- 2022年(令和4年)8月31日:投稿
- 2023年(令和5年)1月24日:全面的にデザインを一新
わかりやすく解説! 就労継続支援事業所のすべて
皆さん、こんにちは。
就労継続支援A型事業所ONE STEP(ワンステップ)利用者のヒラヤマです。
前回の記事を書き上げて、「あー、次のブログ記事、どうしようかな?」と悩んでいると、スタッフの方から「電話での問い合わせや見学などがあったときに、就労継続支援をあまりよく分かっていない方が結構いる」という話を聞きました。
そのときヒラヤマも、「あれ? 自分も就労継続支援とか、A型とか、B型とか、違いが分かってない」ということに気づきました。 ちなみに、皆さんは「就労継続支援って、なに?」と質問されたとき、答えることができますか? そもそも、この単語自体、まだまだ認知度が低いのかもしれません。

「就労継続支援? なんでA型とB型があるの? どうやって利用するの?」
そう思われた方も大丈夫です。
今回は、利用者の私自身も、なんとなくでしか理解していなかった『就労継続支援』についての記事になります。
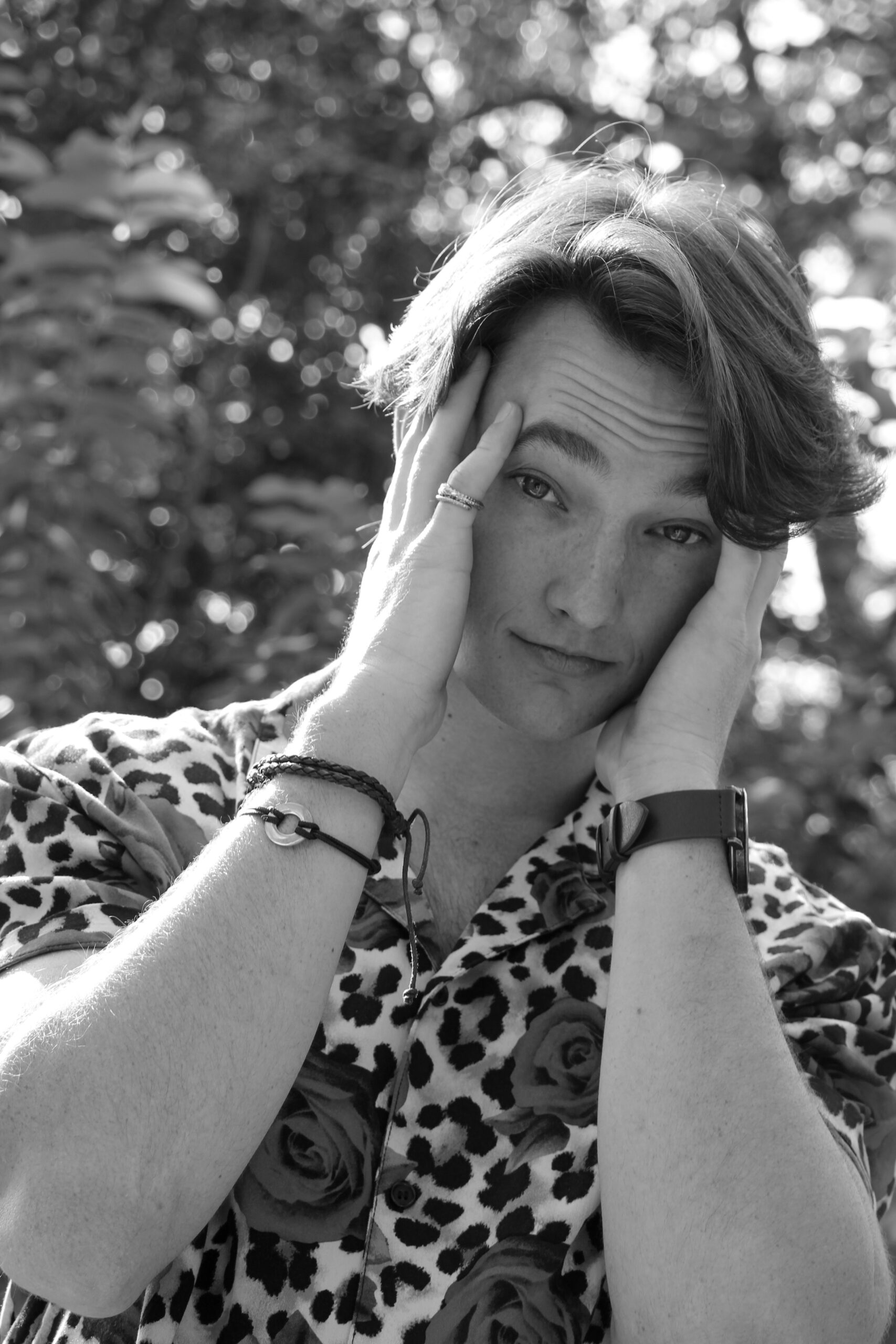
「そもそも『就労継続支援』って言葉自体、初めて聞いた」

「就労継続支援『A型』事業所ってことは、他にも種類があるの?」
そういった疑問を解消できるような内容になっていると思います。
また、今回のブログは、就労継続支援A型事業所ONE STEPを利用しているヒラヤマの実体験を交えながら書いていきます。当事者の話というのは、ネット上を探してもなかなか見つからないので、貴重だと思いますよ?
ホームページに足を運んでくださった方にとって、少しでも有益になれば幸いです。
それでは、いってみましょう!
- 就労継続支援とは?
- A型とB型の違い丨雇用契約・給料(賃金)・有給・年齢対象・対象期間など
- 就労継続支援サービスの利用料の詳細就労継続支援の利用対象の障害や難病の詳細
- 就労継続支援事業所の施設数と一覧
- 就労継続支援の利用対象の障害や難病の詳細
- 就労継続支援を使用するまでの流れ
- 就労継続支援A型事業所・B型事業所の仕事内容
- 就労継続支援事業所の施設数と一覧
- 就労継続支援事業所の人員・設備基準
- 就労継続支援A型・B型のメリット/デメリット
- 就労継続支援は再スタートのための第一歩
就労継続支援とは?

就労継続支援とは、一般就労や就労移行支援事業所での就労が難しい方々などを対象にした障害者福祉法に基づく福祉サービスのひとつです。
大事なことは就労継続支援A型(雇用型)と就労継続支援B型(非雇用型)の2種類があるということです。その違いを、見ていきましょう。
※就労継続支援とよく似たもので就労移行支援という制度があります。
ですが、就労移行支援まで手を広げてしまうと、更にややこしくなってしまいますので、今回は割愛させてください。詳しくはこちらの記事(就労A型 就労B型 就労移行 違い)を見てみてください。
A型とB型の違い丨雇用契約・給料(賃金)・有給・対象年齢・対象期間など
| 就労継続支援A型事業所(雇用型) | 就労継続支援B型事業所(非雇用型) | |
| 雇用契約 | ・雇用契約を結んでいるので、一般企業で勤務するのと同じようなイメージで捉えることができます
【メリット】 【デメリット】 | ・雇用契約を結ばないので、一般企業で就労するのとは違う部分が多い(給料や有給など)ので注意する必要があります
【メリット】 【デメリット】 |
| 給料/賃金 | ○給料は、住んでいる都道府県の最低賃金が基準になります 《具体例》 沖縄県で4時間勤務の場合 最低賃金820円×4=3,200円 これが一ヶ月になるので、 3,200×20日=約6万円 という計算になります ※厚生労働省の調査(P.16)では、令和1年度のA型事業所の月額平均賃金(全国)は78,975円です。 | ○工賃(給料)は事業所によってバラバラです
《具体例》 ※厚生労働省の調査(P.16)では、令和1年度のB型事業所の月額平均(全国)は16,396円です。 |
| 利用料 | 利用料:0円〜最大37,200円
※利用者の世帯状況や就労継続支援事業所により異なります | 利用料:0円〜最大37,200円
※利用者の世帯状況や就労継続支援事業所により異なります |
| 総支給額 | ○基本給−利用料=総支給
※基本給>利用料なので、総支給額がマイナスになることはありません。 | ○基本給−利用料=総支給
※就労継続支援B型事業所は賃金が低いので、基本給<利用料になることがあります |
| 有給 | 雇用契約を結んでいるので、一般企業などと同じように一定期間通所すると、有給休暇が発生します | 雇用契約を結んでいないので、有給休暇はありません。 |
| 対象年齢 | 原則18歳〜65歳未満 | 年齢制限はありません |
| 利用期間 | 規定はありません | 規定はありません |
- 参考URL
就労継続支援サービスの利用料の詳細

| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額 |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯*1 *1…3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税非課税世帯(所得割16万円*2未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く*3 *2…収入がおおむね600万円以下の世帯が対象 *3…入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税世帯の場合、「一般2」となります | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
就労継続支援事業所を利用するときは、A型・B型問わず、利用者側が『利用料』を支払う必要があります。

「雇用関係なのに、なんで利用者がお金を払う必要があるの?」
そう疑問に思う方もいると思います。
その理由は、就労継続支援が『福祉サービス』の一環だからです。
ここが『一般企業と就労継続支援の違い』で、あくまで『国や自治体が提供しているサービスを、利用者が使わせてもらっている』という扱いなのです。
例えるなら『お金を払って職業体験をしている』ようなイメージだと考えていただければと思います。
そして、この利用料は世帯の収入状況によって変動します。
ここで察しのいい方はお気づきになったかもしれませんが、就労継続支援B型事業所など工賃が低い場合、むしろ赤字になる場合があるということです。
さて、ここからがとても重要なところです。
実は利用料を支払わなくてもいい就労継続支援事業所もあるんです。
事業所が、各々の利用者の利用料を負担してくれているんですね。
これ、結構知られていない、とてもお得な情報です。とってもお得な情報です。
大事なことなので、2回言いました!
そして、ヒラヤマが通所している就労継続支援A型事業所ONE STEP(ワンステップ)は利用料が0円(無料)なんです。
例えば、区分が『一般1』の場合、一ヶ月の給料から9,300円が引かれることを意味します。仮に一ヶ月の給料が6万円だったとして、利用料で約1万円が引かれて、実際に貰える給料が5万円になると考えると、その差はとても大きいですよね?
利用料がかからない『生活保護』『低所得』の区分の方なら関係ありません。
ですが、利用料が発生する『一般1』『一般2』の区分に当てはまる方にとっては大きな違いになってくるので、しっかりと事業所に確認することが大事です。
- 参考URL:障害者の利用者負担丨厚生労働省
就労継続支援の利用対象の障害や難病の詳細
| 身体障害 | 視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部障害 |
| 精神障害 | うつ病、双極性障害、統合失調症、転換、パニック障害、適応障害など |
| 発達障害 | ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如・多動症)、LD(学習障害)、知的能力障害(知的発達症) |
| 難病 | 神経・筋疾患、消化器系疾患、循環器系疾患など障害者総合支援法の対象疾病として指定されている疾病に該当するもの(366疾病)
※障害者総合支援法の対象疾病として指定されている疾病に該当するものは、厚生労働省のサイトより確認できます |
就労継続支援を利用するまでの流れ

厚生労働省や市町村のホームページに『就労継続支援の利用手順』が記載されていますが、正直、あまり参考にはしないほうが賢明です。
読んでいくと「いやいや、それはない」と、首を傾げたくなる箇所が多々あります。
なので、内容を噛み砕いて、就労継続支援A型事業所を実際に利用しているヒラヤマ自身の体験談を交えて書いていきます。そうすることで、『よりリアルな就労継続支援を利用するまでの流れ』になると思いますので、ぜひ読んでみてください。
下の表は、大まかな流れです。詳しくは1〜6を確認してください。
| 「事業所探し」と「相談員探し」は、同時並行で行う | |
| ⇩ | ⇩ |
| 働いてみたい就労継続支援事業所をハローワークなどで探す | 住んでいる市町村の『福祉課』で相談事業の一覧を貰う |
| ⇩ | ⇩ |
| ハローワークで、働きたい事業所の見学・体験の予約を取り付ける | その一覧の『下から』電話をかけていき、受け持ってもらえる相談員を探す |
| ⇩ | ⇩ |
| 事業所の見学利用体験 | 相談員と面談・契約 |
| ⇩ | ⇩ |
| 事業所の面接 | 相談員が計画相談利用計画案を役所に提出する |
| ⇩ | ⇩ |
| 役所から障害福祉サービス受給者証が郵送される | ⇩ |
| 届いたサービス受給者証を事業所にもっていき、契約を結ぶ | |
| ⇩ | |
| 事業所で働けるようになる | |
① 働いてみたい就労継続支援事業所を探す
- ハローワークインターネットサービスの『求人区分』内の『障がいのある方のための求人』にチェックを入れて(またはフリーワードで『就労継続支援』と入力して)検索する
- ハローワークの『障がいや病気のある方』を担当している課に置いてあるファイルから探す
1.は、ハローワークが開いていない時間帯などでも探すことができるのが利点です。
その一方、2.は、ネットでは掲載されていない求人がたまに掲載されていたりします。
※念のためですが、『障害者枠』と『就労継続支援A型事業所・就労継続支援B型事業所』は、全くの別物です。混同しないように気をつけてください
② 【最重要】事業所探し(見学・体験・面接)と並行して、相談員を探す
一般企業で働くときと違って、就労継続支援事業所で働く場合、相談員が必須です。
どんなに自分の希望にマッチした就労継続支援事業所を見つけたとしても、相談員がいないと事業所を利用することができません。
そこで相談事業所に電話をするわけですが、この相談員を見つけることこそ、最初にして最大の難関と言っても過言ではありません。
- お住まいの市町村の障害福祉課の窓口で貰える相談事業所の一覧から探す
- 障害福祉サービス等情報検索を使う
国や県が発行しているので、前者の一覧を参考にすることをオススメします。
ただ、何も考えず、馬鹿正直に「就労継続支援を利用したいので、相談員を探しているんですが……。」と、一覧の一番上から電話をかけると悪夢を見ます。
間髪入れずに「新しい利用者を受け持つ余裕がない」と断られるのは当たり前、ようやく面談の予約が取れたと思ったら「2ヶ月後になります」と言われることもザラではありません。実際、ヒラヤマも20は軽く超えて電話しましたからね(苦笑)
そこで、市役所では絶対に教えてもらえない攻略法を使いましょう。ONE STEPで働いているサービス管理責任者の方に教えてもらったのですが、目から鱗でした。
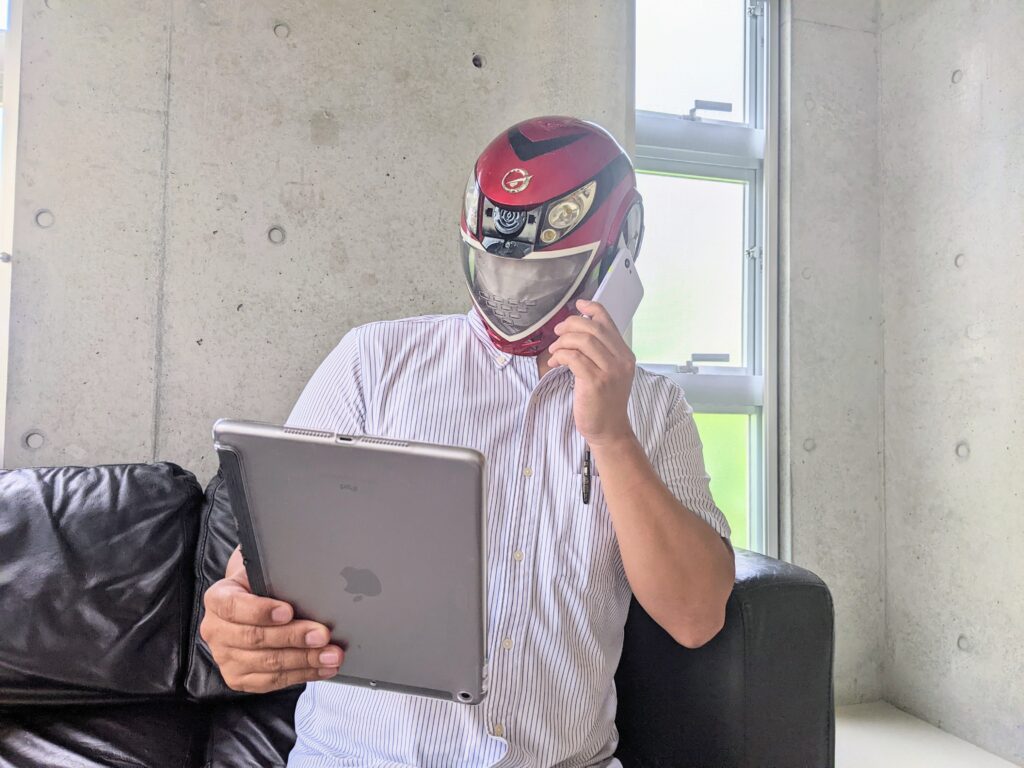
「一覧の一番下から電話する」こと。
ただ、これだけです。
当然、新しい相談事業所は下の方に記載されています。まだ担当している利用者さんも少ないので、新しく受け持って貰える可能性が高いからです。
ですが、これもあくまで可能性ですので、何ヶ所か電話する覚悟はしておいた方がいいかと思います。
なかなか見つからず心が折れそうになることもあるかもしれません。
それでも就労継続支援事業所で働くためには絶対に見つけなくてはいけないので、根気強く頑張りましょう。
※早く見つかることに越したことはありませんが、下記の3〜5の間で相談員が見つかっていなくても大丈夫です。
6の段階で相談員が居て、サービス受給者証を発行して貰えれば問題ありません。
③ 働いてみたい事業所に見学・体験の申し込みをする
基本的に見学無しでいきなり事業所で働くことはできません。
ハローワークを介して、体験の予約をすることになります。
そのとき、自分で聞きにくいことだったり、疑問に思ったことだったりを、自分の代わりにハローワークの職員に電話で確認してもらうこともできます。
利用料や服装のことなど、気になることは前もって聞いておいた方が、のちのち後悔しないと思います。
④ 働いてみたい事業所の見学・体験をする

見学・体験は、事業所によってどんなことをするのか全く違います。
軽く一連の作業を体験するだけの事業所もあれば、がっつり丸一日作業する事業所もあります。
こういったところも事前に聞いておくと、利用者さんと事業所ですれ違いが起きずに済みますね。
相談員さんが見つかっている場合、一緒に事業所に行くことも可能です。
ずっと一緒にいてくれるわけではありませんが、最初だけ居てくれるだけでも不安は解消されるのではないでしょうか
⑤ 働いてみたい事業所の面接を受ける
すべてを開示する必要はありませんが、逆に「マイナスなことを言うと不合格になるかも……。」と、ご自身の障害や病気のことを極端に隠す必要もありません。
就労継続支援を利用する条件が『障がいや病気の方』である以上、利用者さんになにかしらの障がいや病気があることは知っているので、事業所側も理解を示してくれます。
空白期間なども「病気の療養で〜」と素直に言ってしまった方がいいと思います。ヒラヤマはそうしました
⑥ 働いてみたい事業所と契約する
ここで重要なのは、合格に至ったとしても、『利用者さんと就労継続支援事業所との契約には、障害福祉サービス受給者証が必須』ということです。
ですが、もし障害福祉サービス受給者証の発行が間に合わず手元にない場合でも、受給者証が郵送されるまで、書類での契約を待ってくれますので安心してください。
事業所から口頭での合格を貰う⇨実際に書面での契約まで、タイムラグがあっても大丈夫です。
就労継続支援A型事業所・B型事業所の仕事内容
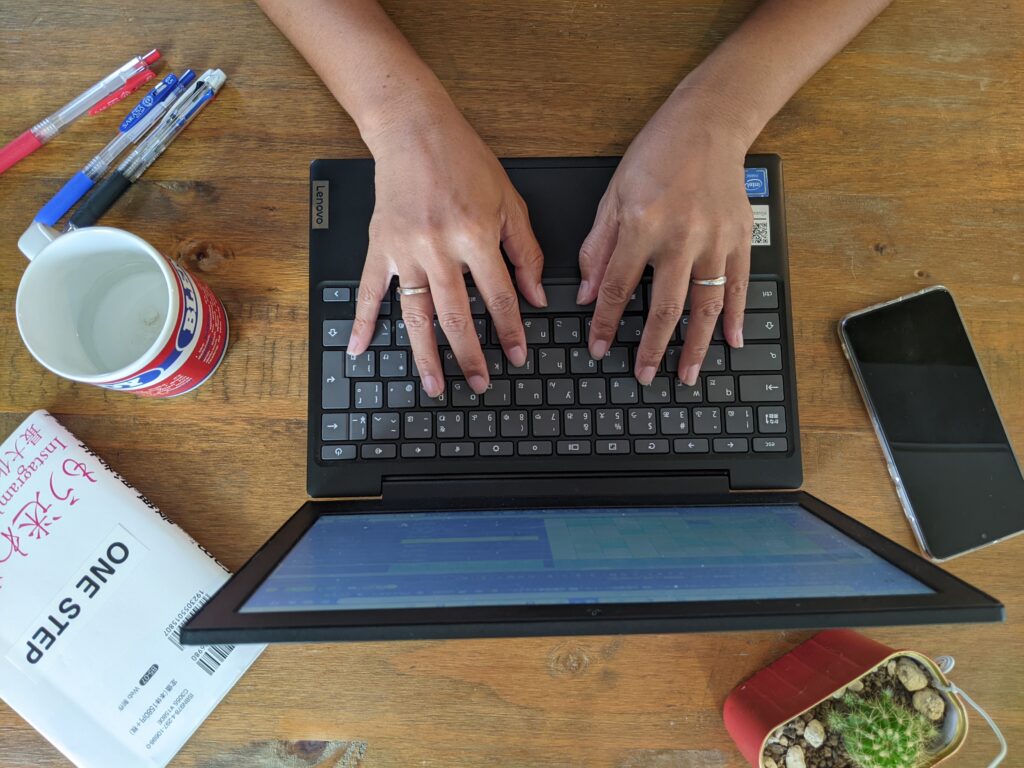
仕事内容に関しては、手芸作業・清掃作業・調理補助・ホテルでのベッドメイキング・農作業・軽作業・データ入力など、就労継続支援A型事業所と就労継続支援B型事業所で、そこまで明確な区別がされているわけではありません。
ただ、就労継続支援A型事業所は『雇用契約を結んでいる』ということもあり、就労継続支援B型事業所に比べると難しい仕事内容になっているイメージです。
最近は、eスポーツを取り入れている就労継続支援型事業所もあったりします。
詳しくは、ハローワークインターネットサービスの『求人区分』内の『障がいのある方のための求人』にチェックを入れて(または、フリーワードで『就労継続支援』と入力して)検索してみてください。
そこで、どのような仕事の求人があるのか確認することができます。
ただ、あくまでネットの情報や求人情報だけで早合点するのは駄目です。
実際に体験などを通じて『雰囲気』などを確認することは欠かせません。
※念のためですが、『障害者枠』と『就労継続支援A型事業所・就労継続支援B型事業所』は、全くの別物です。混同しないように気をつけてください。
就労継続支援事業所の施設数と一覧
厚生労働省のホームページによると、国保連データ(令和3年1月)では、全国での就労継続支援A型事業所が3,922箇所(利用者数:75,571人)、就労継続支援B型事業所が13,828箇所(利用者数:282,409人)とのことです。
沖縄県の障害福祉サービス指定事業所情報(令和4年7月1日)によると、事業所の数は就労継続支援A型事業所が125箇所、就労継続支援B型事業所が379箇所あります。
他にも障がい者就労支援情報や障害福祉サービス等情報検索といった検索サイトもあるので、検索してみることをオススメします。
就労継続支援A型事業所の人員・設備基準
就労継続支援事業所を運営するためには、必ず満たさなければならない人員や設備の基準が定められています。
なかでも、職業指導員および生活支援員(生活指導員)、サービス管理責任者、管理者は1人ずつ、必ず配置されていなければいけない規則があります。
ここは、事業所側のお話になるので、そこまで利用者さんが深く知る必要はありません。
ですが、『ちゃんと基準を守って、人員を配置している=ちゃんとした事業所』という、事業所を判断する材料のひとつにはなるかと思いますので、参考程度に頭の片隅に留めておいてください。
とはいえ、スタッフの方がどんな仕事をしているのか気になる方もいるかと思いますので、一例として、ONE STEPのブログでも取り上げている記事があるので、こちら(職業指導員の仕事内容)を見てみてはいかがでしょうか?
就労継続支援A型・B型のメリット/デメリット

ここまでで、ある程度、就労継続支援A型事業所と就労継続支援B型事業所については理解して頂けたのではないでしょうか?
そうすると、次は「じゃあ、就労継続支援A型事業所と就労継続支援B型事業所、どっちを選べばいいの?」という悩みが生まれてくるかと思います。
そこで、就労継続支援A型・B型のメリット/デメリットを改めて振り返ってみましょう
| 就労継続支援A型事業所 | 就労継続支援B型事業所 | |
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
大前提として、就労継続支援A型・B型ともに利用者さんの体調に配慮してくれます。
もちろん、「なに休んでるんだ!!」と怒鳴られることもないので安心してください。体調が優れないときは無理せず、休むことができます。
そのうえで、個人的には、このような判断基準で良いかと思います。
- 就労継続支援A型事業所
- 長時間働くことにそこまで不安のない方
- 就労継続支援B型事業所
- 長時間働くことに不安を感じる方。少しの時間・日数から通所して慣れていくことを優先したい ただ最終的な判断は『事業所を見学してみてから下すこと』が大事なことには変わりありません。
例えば、B型を希望している方がいて、気になっている事業所がA型だったとします。
その場合、ものは試しで体験してみましょう。
いざ実際に体験してみて「自分でもできるかもしれない」と思えるのなら、A型からスタートしてみても全然良いと思います。その方にとって、仕事内容の合う/合わない次第では、B型よりA型の方が体力的にも精神的にも楽な場合もあります。
また、体験することで、「事業所を選ぶとき、自分が本当に重視していることはなにか?」ということが分かってくることもあるからです。
就労継続支援は再スタートのための第一歩

今回の記事はいかがだったでしょうか?
『就労継続支援』『就労継続支援A型事業所』『就労継続支援B型事業所』、そこに関わってくる制度などは、ただそのまま書くだけでは難しくなってしまいます。
そこで、ヒラヤマ自身の体験談を交えることで、できるだけ読みやすく、分かりやすく、まとめたつもりです。
ですが、この記事はあくまで『就労継続支援事業所の一側面』でしかありません。
実際に、その就労継続支援事業所に足を運んでみて、一日体験などをして、初めてその事業所について知ることができると思います。
事業所の雰囲気や立地、人間関係、どんな人たちが通所しているのか、スタッフの人柄……などなど、求人やホームページだけでは分かり得ない部分が多いからです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
それではまた次回、お会いできることを願って……。
今回の記事の執筆者はONE STEP(ワンステップ)利用者のヒラヤマでした。


1 Comment
Comments are closed.