マイナンバーカード更新が必要な人へ
更新を意識すべきタイミングは、すぐそこ!
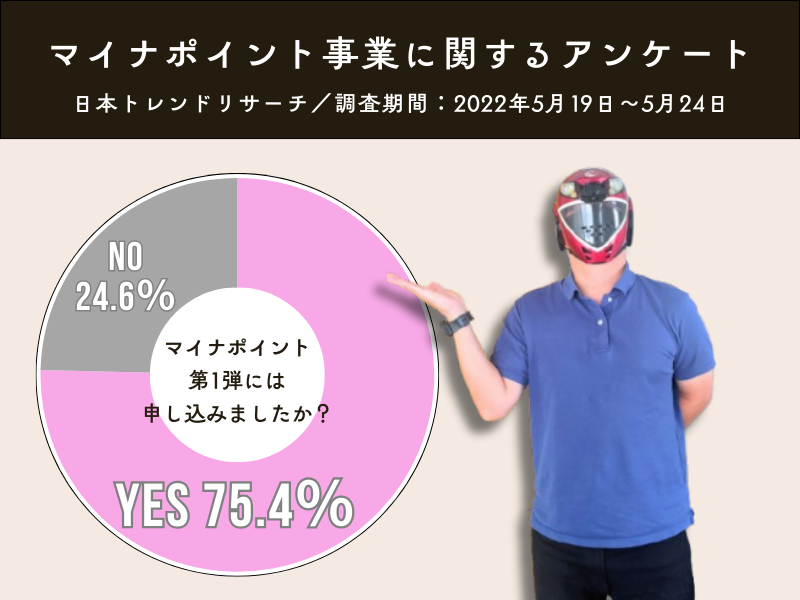
みなさん、こんにちは。
就労継続支援A型事業所ONE STEP利用者のヒラヤマです。
突然ですが、皆さんは「運命の日」が刻々と近づいていることに気づいていますか?
恐らく、この「運命の日」が頭からすっぽり抜け落ちている方も少なくないと思います。(ヒラヤマ自身もそうでした)
しかし、避けて通ることはできません。必ず向き合うことになります。
そのとき、多くの人が、きっと、こう思うでしょう。

「暗証番号? 覚えてるわけないだろ!」

「利用者証明用が4桁? 署名用が6〜16桁? なにそれ!?」
というわけで、今回は「マイナンバーカードの電子証明書の有効期限と更新手続き」について解説します。

「なぜ、いまマイナンバーカードの更新?」
と疑問に思った方も多いでしょう。
実は、マイナンバーカードを作った方の多くは、マイナポイント第1弾(2020年9月〜2021年12月)の時期にカードを取得しています。
そのときに発行された電子証明書は、年齢に関係なく発行日から5回目の誕生日までが有効期限です。つまり、そろそろ更新が必要になってきているのです。
まずは、このマイナポイント事業の概要とマイナンバーカードの基本的な機能を振り返り、なぜ更新が必要なのかを理解していきましょう。
“懐かしのあの頃” – マイナポイント事業を振り返る

皆さん、マイナポイント事業は覚えていますか?
ざっくりいうと、「現金〇〇円分ポイントあげるから、マイナンバーカードを登録してね」というキャンペーンです。
当時は、俳優の舘ひろしさんや現・日本ハムファイターズ監督の新庄剛志さん、芸人のずん・飯尾和樹さんなどが出演するCMが連日放送され、大きな話題となりました。
以下の表は、マイナポイント事業の時期と概要です。
| 時期 | 概要 |
| 第1弾 (2020年9月〜2021年12月) |
|
| 第2弾 (2022年〜2023年) |
|
そして、この第1弾でマイナンバーカードを作った方に注意してほしいのが、カードに搭載された電子証明書の有効期限です。
マイナンバーカード本体はまだ有効でも、電子証明書の期限は発行日から5回目の誕生日までと決まっており、そろそろ更新時期に差し掛かっています。
ですので、ここからは、電子証明書の有効期限や更新手順、福祉系での便利な使い方について解説していきます。
マイナンバーカードとは?

マイナンバーカード(正式には「個人番号カード」)は、日本国内に住むすべての人が持つことができるICカードです。
行政手続きの簡略化や、本人確認の効率化を目的として作られました。
見た目と基本機能
- 顔写真付きのプラスチックカードで、身分証明書としても利用可能
- 搭載されているICチップには、さまざまな情報や電子証明書が記録されています
主な機能
1.電子証明書
- オンラインでの行政手続きやマイナポータルへのログインに必須
- 署名や本人確認の電子的証明として使われます
2.健康保険証としての利用(希望者のみ)
- 医療機関でカードを提示するだけで、従来の保険証と同様に利用可能
- 手続きが簡略化され、医療費の自己負担情報もオンラインで確認できる
3.公金受取口座登録
- 給付金や助成金、児童手当などの振込口座として登録可能
- マイナポイント事業の利用にも紐づく
4.コンビニ交付サービス
- 住民票、印鑑証明、課税証明などの書類を全国のコンビニで取得可能
- 窓口に行く手間を省き、必要なときにすぐ取得できる
有効期限
- カード本体
- 20歳以上:発行から10回目の誕生日まで
- 20歳未満:発行から5回目の誕生日まで
- 電子証明書
- 年齢に関係なく、発行日から5回目の誕生日まで
- カードは有効でも、電子証明書が期限切れだとオンライン手続きや福祉系サービスは使えません
取得方法
- 市区町村の窓口やオンラインで申請可能
- 受け取りの際には本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)が必要
マイナンバーカード2つの有効期限
(本体・電子証明書)
実は、マイナンバーカードには、2つの有効期限があります。
この「2つの有効期限がある」という部分が、非常に混乱しやすいです。
つまり「カードは有効でも、電子証明書は無効になることがある」という不可解な事態も考えられるのです。
「だったら、どっちも5年の有効期限でいいじゃん」
と思わずにはいられません(当然、ヒラヤマもその一人です)。
こういうところが「お役所仕事」と揶揄される所以かと思いますが……。(苦笑)
| 種類 | 有効期限の目安 | 影響 |
| カード本体 |
|
|
| 電子証明書 |
|
|
マイナンバーカードの電子証明書の更新方法
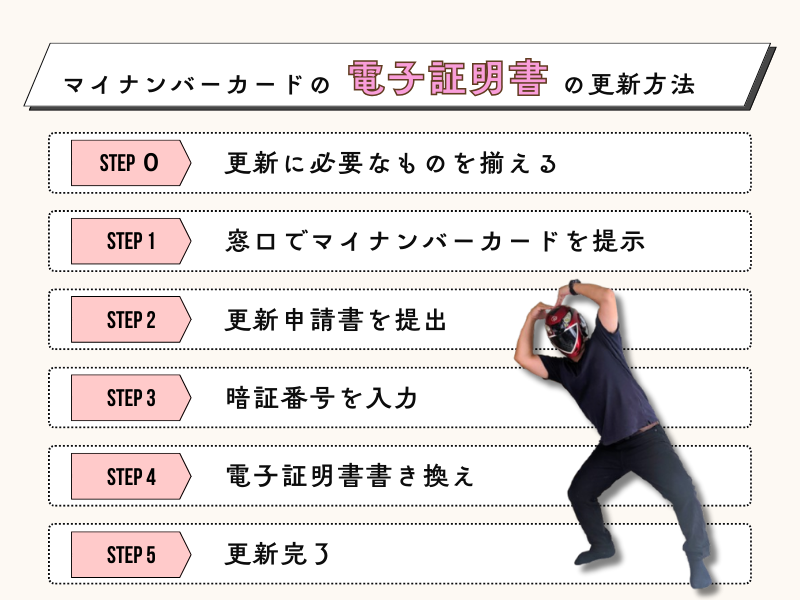
電子証明書は、有効期限が切れる前に、お住まいの市区町村窓口で更新します。
残念ながら、自宅やオンラインでは更新できないので、気をつけましょう。
更新に必要なもの
「せっかく貴重な時間を割いて市区町村窓口に出向いたのに、必要なものが足りないせいで無駄足になった」といった徒労にならないために、更新に必要なものはしっかり揃えておきましょう。
- マイナンバーカード本体
- 更新通知(届いた場合)
- 暗証番号
- 利用者証明用(数字4桁)
- 署名用(英数字6〜16桁)
電子証明書の更新が必要な理由
マイナポイントをきっかけにカードを作った方は多いと思いますが、そのカードに搭載されている電子証明書には有効期限があります。
実はマイナンバーカード本体の有効期限と違い、電子証明書は発行から5回目の誕生日までしか有効ではありません。
「カード自体はまだ使えるのに、電子証明書が期限切れでオンライン手続きができない」
そんなトラブルを防ぐために、期限が来る前に更新しておくことが大切です。
ここからは、実際の更新手順を図解イメージ付きで分かりやすく解説していきます。
更新手順の図解イメージ
マイナンバーカードの電子証明書更新は、窓口で行うシンプルな手続きです。
手順に沿って進めれば、10〜20分程度で完了します。
暗証番号がわからない場合でも、窓口で再設定できるので安心です。
| STEP 1 | 窓口でマイナンバーカードを提示 | まずは窓口でカードを提示します。 専用読み取り機でカード情報を確認し、手続きが始まります。 |
| STEP 2 | 更新申請書を提出 | 窓口で渡される申請用紙に必要事項を記入して提出します。 記入内容は基本的な氏名や連絡先などです。 |
| STEP 3‐A | 暗証番号がわかる場合 | 利用者証明用の4桁、署名用の6〜16桁の暗証番号を入力します。暗証番号がわかればスムーズに進みます。 |
| STEP 3‐B | 暗証番号がわからない場合 | 窓口で新しい暗証番号を設定します。 再設定には本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)が必要です。 |
| STEP 4 | 電子証明書書き換え | 新しい電子証明書が発行され、有効期限が更新されます。 この時点でオンライン手続きや福祉サービスにすぐ使える状態になります。 |
| STEP 5 | 更新完了 | 手続きは10〜20分程度で終了します。 これで電子証明書の有効期限は延長され、安心して各種サービスを利用できます。 |
福祉サービスでのマイナンバーカードの便利な活用方法
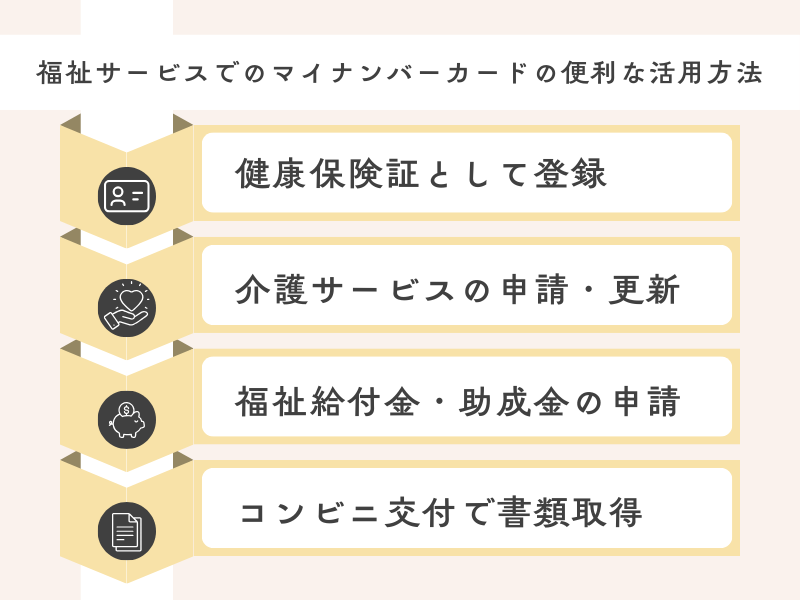
マイナンバーカードがあれば、福祉サービスの手続きがオンラインで完結し、時間や移動の負担が大きく軽減されるのが最大のメリットです。
日常生活の中でどのように活用できるのか、具体的に見ていきましょう。
健康保険証として登録
マイナンバーカードは、健康保険証としても利用できます。
医療機関でカードを提示するだけで手続きが完了し、これまで必要だった書類の提出や確認の手間が省けます。
医療費の自己負担額や診療履歴もオンラインで確認できるので、通院や薬の管理がよりスムーズになります。
介護サービスの申請・更新
介護サービスの利用申請や更新も、マイナンバーカードを使えばオンラインで完結します。
窓口に行かずに、自宅から手続きを済ませられるため、移動が大変な方や高齢者にとって大きなメリットです。
福祉給付金・助成金の申請
児童手当や各種福祉給付金・助成金の申請も、マイナンバーカードを使えばオンラインで行えます。自宅で手続きを完結させ、口座振込で受け取れるので、手続きの負担を大幅に軽減できます。
コンビニ交付で書類取得
住民票、印鑑証明、課税証明などの必要書類も、全国のコンビニで取得可能です。
窓口で長時間待つ必要がなく、必要なときにすぐに取得できるので、福祉サービスの申請や手続きがより手軽になります。
マイナンバーカード電子証明書の有効期限切れに注意!
忘れずに更新を!
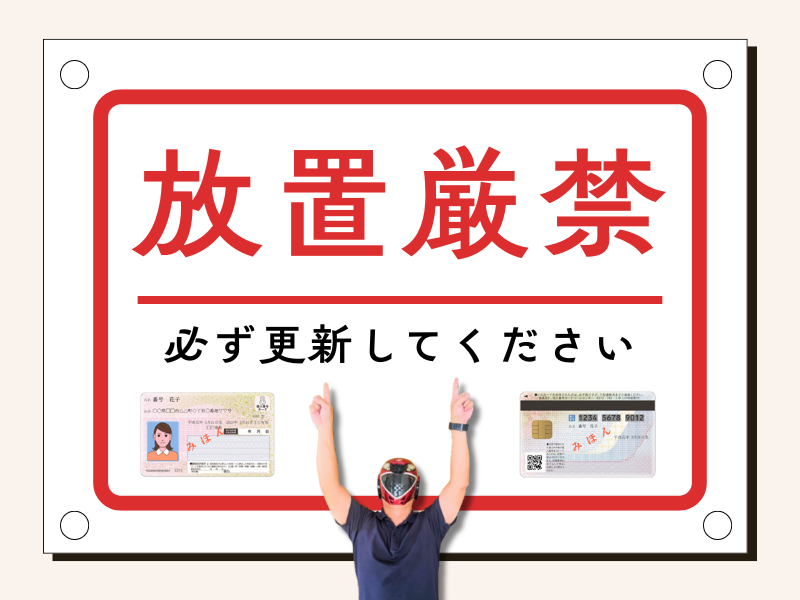
電子証明書の有効期限は「発行から5回目の誕生日まで」と少し特殊なルールなので、「気づいたら切れていた……。」という人も少なくありません。
ヒラヤマ自身も、

「暗証番号? え、そんなの覚えてないよ!」
と、慌てた経験があります。
だからこそ、この記事を読んだ“今”がチャンス。
ぜひ一度、カードの有効期限を確認してみてください。
ちょっとした準備で、これからもスムーズに福祉サービスや日常の手続きを使えますよ。

