- 2025年(令和7年)7月16日:投稿
AIが書く時代に、人間がブログを書く意味を見つめ直す
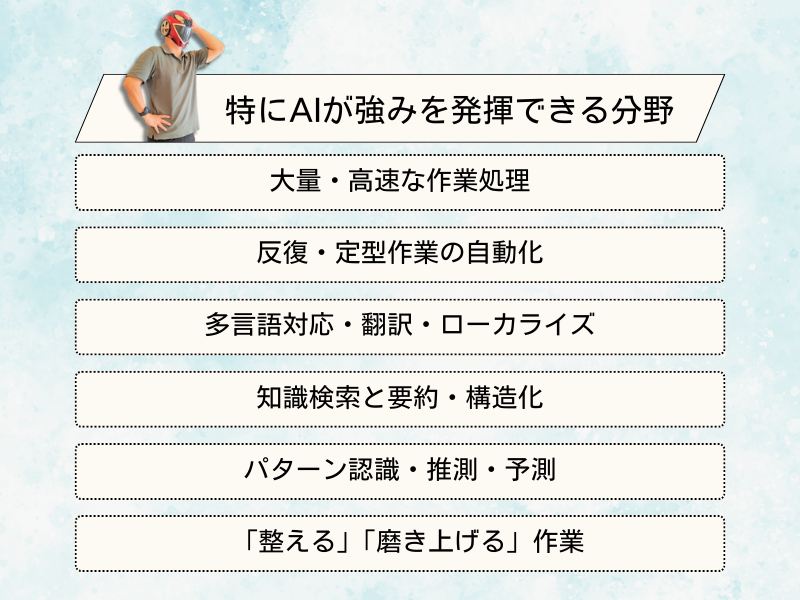
みなさん、こんにちは。
就労継続支援A型事業所ONE STEP(Instagram/Facebook/X(旧Twitter))に入所しているヒラヤマです。
2022年12月、世界に衝撃を与える技術的なブレイクスルーが起こりました。
そう、生成AI「Chat GPT」の登場です。
「Chat GPT」の登場を皮切りに、次々と新たな生成AIが誕生しました。
今もどこかで新機能の実装や、進化を続けています。
技術革新の波により、いまや私たちの生活や仕事の多くが、AIで代替できるようになりました。
AIの躍進により、近い将来、廃業や縮小を迫られる職業も決して珍しくありません。
もはや「AIを使いこなすこと」が前提となりました。
「AIを使わない」という選択肢は、現実的ではなくなってきています。
なかでも、以下の項目では、特にAIの強みが発揮できることもあり、もはや人間の出る幕はありません。
| 大量・高速な作業処理 |
|
反復・定型作業の自動化 |
|
| 多言語対応・翻訳・ローカライズ |
|
| 知識検索と要約・構造化 |
|
| パターン認識・推測・予測 |
|
| 「整える」「磨き上げる」作業 |
|
そして当然ながら、「ブログ記事の生成」もAIが強みを発揮できる分野です。
記事の構成、見出し、文章のトーン設定、画像生成、SEOキーワード。
AIに任せれば、ものの数分で、形の整った記事が完成します(ヒラヤマもたびたびお世話になっています)。
仮に内容がいまいちだったとしても、「ここをもっと詳しく」「ここは省略して」と、その都度、修正指示を出せば、即座に対応。
また、どんなにリライトさせたところで、人間とは違い、AIはキレたりしません。
(※AIであっても、言葉の丁寧さやフランクさで、返答するときのニュアンスは変わってくるので、言い方のニュアンスに気をつける必要があるかもしれませんが)
当然、リライトの速度は、人間とは比べ物になりません。
記事の内容の真偽に関しては「100%正しい」とは限らないですが、それはAIに限った話ではありません。人間が書いた記事でも同じことです。
そう考えると、SNSやマーケティング界隈で聞かれる以下のような声にも、頷かざるを得ません。

「ChatGPTに書かせればいい」

「AI生成なら、外注より安いし早い」

「正直、AIが書いてくれるなら、それでいい」
諦めとも取れるような声が、私の身の回りでもちらほら聞こえるようになってきました。
正直なところ、ヒラヤマもそう思っている節があります。
創造主と同じ種族に対する敬意のようなものがあるのか、AIは人間をやたら持ち上げる傾向があります。ですが、悲観主義者のヒラヤマからすると、「AIでできないのは、もはや肉体労働くらいでは?」とさえ感じてしまいます。
『ターミネーター』『マトリックス』などのように、機械が人間に反旗を翻したり、機械が人間を支配したり、そういった世界も現実味を帯びているかもしれません。
まあ、ヒラヤマ個人の偏った未来予想はさておき。
では本当に「人間がブログを書く意味」は、もうないのでしょうか?
本記事では、「AIがブログを書けるようになった今、人間にしかできない役割とは何か?」をテーマに、できるだけ具体的な視点から掘り下げていきます。
【 目 次 】
- 生成AIの代表例(ジャンル別)
- 文章生成(自然言語処理系)
- 画像生成
- 動画生成(映像)
- 音声・ナレーション生成
- コード・開発支援(プログラミング系)
- その他ジャンル(資料作成・音楽・3Dなど)
- AI全盛時代に、人間が記事を書く“価値”を残すには
- AIで事足りる記事とは?
- 人間にしかできないこととは?
- 人間らしさを構成する要素とは?
- 人間の意図を伝える技術とは?
- 人間がブログを書く“意味”をもう一度問い直すとき
生成AIの代表例(ジャンル別)

まずは2025年現在、生成AIでどのようなことができるのかを把握しましょう。
あまりにも多種多様な生成AIが次々と登場しており、その数の多さに驚かれる方も多いはずです。
文章生成(自然言語処理系)
| ツール名 | 概要 |
| ChatGPT(OpenAI) | 会話形式で高精度なテキストを生成。 多目的に使用可能。 |
| Claude(Anthropic) | 安全性重視の設計。 要約や創造的な文章生成が得意。 |
| Gemini(旧Bard/Google) | 検索連携が強み。 Google Workspaceと統合可能。 |
| Perplexity AI | 回答に情報源を表示する検索特化型チャット。 |
| Jasper AI(旧Jarvis) | マーケティングやSEO向けのライティングに特化。 |
画像生成
| ツール名 | 概要 |
| Midjourney | アートスタイルに強い。 Discord経由で操作。 |
| DALL·E(OpenAI) | 写実・イラスト表現ともに対応。ChatGPTと連携。 |
| Stable Diffusion | オープンソース。 ローカルでカスタムモデルも可能。 |
| Adobe Firefly | 写真・グラフィック向けの生成。 商用利用に強い。 |
| Canva Magic Media | デザイン統合型の画像生成。 テンプレも豊富。 |
動画生成(映像)
| ツール名 | 概要 |
| Sora(OpenAI) | テキストからリアルな動画を生成 (プロトタイプ段階) |
| Runway ML | 簡単な操作で動画生成・編集が可能。 個人クリエイター向け。 |
| Pika | 高速でアニメやCG風動画を生成。 自然な動きに強い。 |
| Synthesia | AIアバターによるナレーション動画作成に特化。 |
| HeyGen | 顔出し不要で人物解説動画を生成できる。SNS動画向け。 |
音声・ナレーション生成
| ツール名 | 概要 |
| ElevenLabs | 多言語・多感情に対応した自然な音声生成。 |
| Voice AI | リアルタイムで音声変換。 配信・通話向け。 |
| Coqui | オープンソースで音声合成エンジンを構築可能。 |
| Google Cloud Text-to-Speech | 商用利用に強く、高品質な音声をAPI経由で生成。 |
コード・開発支援(プログラミング系)
| ツール名 | 概要 |
| GitHub Copilot | VS Code等でコードをリアルタイム補完。 |
| CodeWhisperer(AWS) | AWS環境に特化したコード補完AI。 |
| Replit Ghostwriter | Web上の開発環境でAI補助を提供。 |
その他ジャンル(資料作成・音楽・3Dなど)
| ジャンル | ツール名 | 概要 |
| 資料作成 | Tome / Gamma | スライドやプレゼン資料を自動生成。 |
| 音楽生成 | Soundraw / AIVA / Suno AI | 著作権フリーの楽曲生成が可能。 |
| 3D生成 | Luma AI / Kaedim | テキストや画像から3Dモデルを作成。 |
| Web制作 | Framer AI / Wix ADI | サイト構成・デザインをAIが提案・生成。 |
AI全盛時代に、人間が記事を書く“価値”を残すには
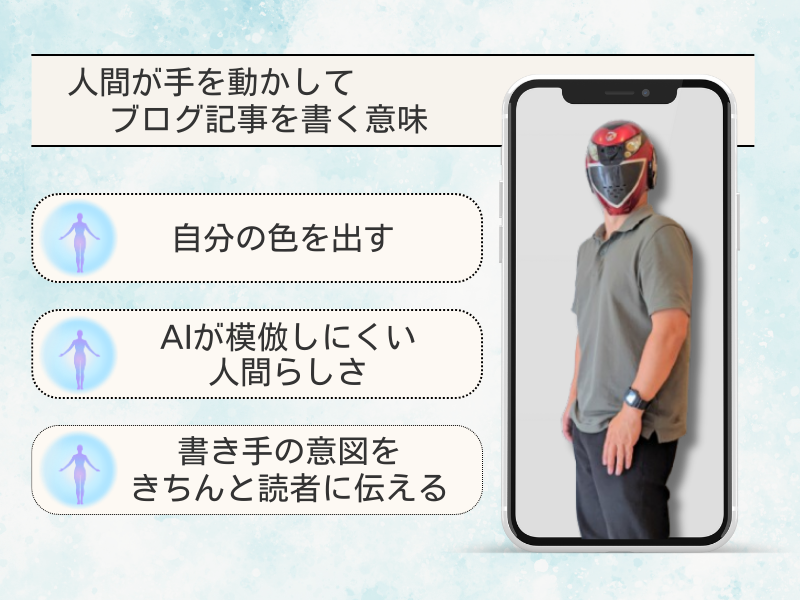
ここまで、「生成AIの多様さとその圧倒的な能力」について、理解して頂けたかと思います。
では、いよいよ本題に入りましょう。さて、ここからが本題です。
「AIがこれだけ優れている今、人間が手を動かして文章を書く意味とは何か?」
この問いについて、ヒラヤマ自身がAIと何度も対話を重ねた末に辿り着いた結論を、ここからお話ししていきます。
AIで事足りる記事とは?
まず、大前提として知っておいてほしいのは「AIで十分な記事は確かに存在する」ということです。具体的には、以下のような特徴を持つ記事です。
―― AIで十分な記事の特徴 ――
- 感情の深掘りが不要
- 共感よりも結論が重視される
- 書き手が誰か、読者が気にしていない
- 「人間らしさ」がブランド価値になっていない
こういった記事では、AIが得意とする論理性・情報処理能力が最大限に活かされます。
例えば、以下のようなものが該当します。
- 商品スペックの比較記事
- 法制度やサービスの説明記事
- 汎用的なノウハウ・ハウツー記事
これらに関しては、人間が書かなくても問題はないでしょう。
人間にしかできないこととは?
では、人間が手を動かして書く意味はどこにあるのでしょうか?
その答えは、「自分の色を出すこと」にあります。
「自分の色を出す」とは、例えば、以下のようなことです。
- 「自分の色」の具体例読者の立場やニーズを大切にしつつ、自分の視点や感情を自然に織り交ぜる
- 押し付けがましくない、共感を呼ぶ程度の主張や意見
- 文章全体が読みやすく伝わりやすいことを優先して、過剰な個性は避ける
つまり「邪魔にならない、でも確かに人間っぽさが滲む」ような文章表現です。
こういった人間らしい表現は、AIが最も苦手とする領域のひとつです。
人間らしさを構成する要素とは?
ここでは、「AIが模倣しにくい人間らしさ」の構成要素をいくつかご紹介します。
- 人間の強みとなる文章表現の要素
- 文章の違和感を察知する力
- 例:流れと合わない比喩やトーンのズレに気づき、修正できる
- 言い切りや曖昧さのニュアンス調整
- 例:「たぶん」「おそらく」といった曖昧さの使い分け
- 矛盾や葛藤の表現
- 例:「以前はこう思っていたけど、今はこう考えるようになった
- 読者との目線共有
- 例:「これ、みなさんも経験ありませんか?」のような語りかけ
- ツッコミ・ひとりごと
- 例:「いや、ほんと勘弁してほしいですよね(笑)」などのゆるさ
- 失敗談や弱さの表現
- 例:「実は〜で失敗しました」のような共感を生む開示
- 文章の違和感を察知する力
人間の意図を伝える技術とは?
さらに、読者との信頼関係を築くためには「書き手の意図」が読者にきちんと伝わることも不可欠です。
- 意図を伝えるための工夫
- 読者の「状況・疑問・感情」を想像して寄り添う
- 意図や導入文や見出しで明確に示す
- 読者の疑問に先回りして答える構成にする
- 情報を広く載せるより、伝えたいテーマに一点集中する
- 自分の体験や感情をしっかり言語化して文章に滲ませる
こうした工夫が積み重なることで、読者との「距離」が近づき、信頼が育ち、やがてファンにも繋がります。
人間がブログを書く“意味”をもう一度問い直すとき
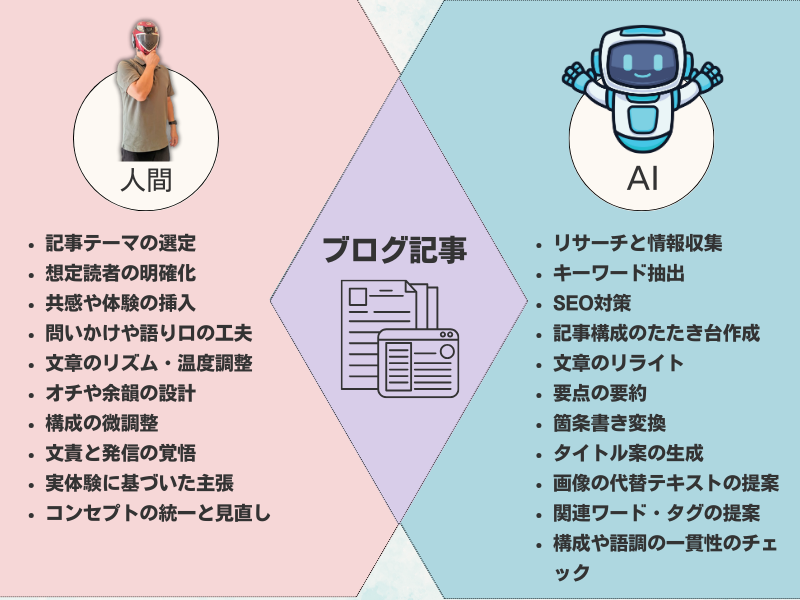
正直なところ、読者の多くは「この記事をAIが書いたか人間が書いたか」なんて、ほとんど意識していないかもしれません。
それでも、もし「人間が書く意味」を持たせたいのであれば、それ相応の工夫や姿勢が必要になります。
たとえ1本の記事の中で、「AI:人間=99%:1%」という構成だったとしても、その“わずか1%の人間の関与”が、読者の心に届くかどうかの違いを生む可能性もあるのです。
ちなみにヒラヤマは、AIに少しだけ意地悪な質問をしてみました。

「カレーを作ったとして、人間は“じゃがいもの皮を剥いただけ”、AIがそれ以外のすべての工程を担当したら、それってもうAIのカレーじゃない?」
するとAIは、こう返してきました。

「カレー作りでいえば、たとえAIが大部分を担っていたとしても、人間が“味の決め手”や“方向性”を握っている限り、人間の関与が不可欠だと言えるでしょう。
ただし、役割の重さを考えれば、無理に人間の重要性を強調しているように感じるのも自然です。
こうした感覚的なズレを、どう埋めていくか――一緒に考えてみませんか?」
……完敗でした。
今回の「ヒラヤマ vs AI」、判定はAIの圧勝ということで締めくくらせていただきます。
それでも、こうやって問い続けることそのものが、人間だからこそできることなのかもしれません。

